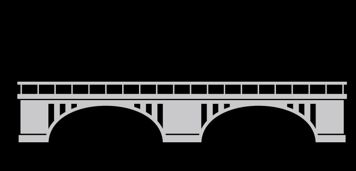日本橋モラロジー事務所
NIHOMBASHI
MORALOGY
- トップページ
- コラム・メインページに戻る
- 曽根惠子さんの『明るくなれる生活アドバイス』
曽根惠子さんの『明るくなれる生活アドバイス』

【相続QアンドA】③ Q 遺言書は公証役場でないと作れない? (2023.12)
A 公正証書遺言は公証役場で作る遺言書です。本人と証人が公証役場に出向いて遺言書を作成します。けれども病気のため入院中であったり、高齢により老人ホームに入所するなどして出かけにくいなど、本人が公証役場に出向けないこともあることでしょう。 そのような事情がある場合は、公証人と証人が、ご自宅、病院、老人ホーム、ホスピスなど、遺言者のもとに出向いて、そのお部屋で公正証書遺言を作ることができます。また、公証役場に出向く場合も、最寄りでなくてもよく、出向いたところで遺言書が作れます。千葉、さいたま、神奈川の方が東京で。関西や九州の方なども東京の公証役場で作ることができるということも知っておきましょう。
【相続QアンドA】② Q 要介護だと遺言書は作れない? (2023.11)
A 介護が必要な状態が「要介護」で、“身体的な介護の度合い“をいいます。要介護認定を受けるとご本人も、ご家族も「認知症」になったという判断をしてしまい、遺言書は作れないと思われがちです。けれども、遺言書は“本人の意思”が明確であれば要介護でも作ることはできるのです。公正証書遺言であれば公証人が面前にて意思確認をして判断をしますので、効力のある遺言書が作れます。たとえば骨折などから歩行が困難となり、「要介護5」の認定を受けている方でも、通常の会話ができ、意思も明確でサインもできる場合は、問題なく公正証書遺言が作れます。「要介護」=「認知症」ではないことを知って、遺言書作りをしましょう。
【相続QアンドA】① Q ずっと可愛がって一緒に暮らしてきたペットに財産を残せますか?(2023.10)
A 残念なが゜ら、ペットに財産を残すことはできません。家族同様に暮らしてきたペットであっても、ペットには人格がないので、直接、財産を残すことはできません。けれども、自分が亡くなった後のペットのことが気になるのは当然のことでしょう。その場合は、「遺言書」で「ペットの世話をしてもらうために財産を渡します」とお願いしたい人を指定して、託すことはできます。その場合は、一方的に書いても実現しないこともありますので、事前に了解をしてもらっておくことが必要です。 また高齢になり、ペットの世話ができなくなることもあるかもしれません。そうした場合も、事前に引き取り手を探しておくなど、準備しておくようにしましょう。親族に託せる場合はいいのですが、託す人がいない場合は引き受けてくれる団体などもありますので、事前に探して相談するなどしておくと安心です。
Vol.38 自分の言葉で遺言書が作れる(2023.08)
Hさんの父親は70歳で遺言書を作られ、10年後の80歳で亡くなりました。母親はそれからさらに数年経ち、90歳目前。今年になり、骨折して入院することがあり、今の時期に作っておきたいとなりました。母親が自ら言い出したことなので、財産の分け方の意思も明確ではあるのですが、それを自分で形にすることは簡単ではありません。そこでHさん姉妹がサポート。公証人に相談すると母親が使っている表現で記載し、詳細は別紙にすればいいと。普段の呼び方で不動産の渡し方を話しできたことで、公証人も母親の意思確認ができたいと判断し、公正証書遺言は無事に出来上がりました。Hさんの母親のように、本人の言いやすい表現で公正証書遺言が作れることで。堅い表現ではなく、柔軟に対応してもらえることがわかりました。公証人も、証人の夢相続もいろいろと段取りをしたお陰で、スムーズに遺言書が作成でき、安堵した次第です。
Vol.36 銀行はお客様のことは救わない?(2023.07)
「仕組み債」のリスクを十分に説明せずに顧客に販売したと関東財務局が地方銀行2行と証券会社の3社に業務改善命令を出しました。銀行も、証券会社も、顧客に不利益な営業をしていることが判明し、行政処分となったようです。相談に来られたお客様も銀行に依頼して苦労をされています。父親が銀行で遺言書を作成しており、相続になって、遺言執行を依頼。底地の売却も依頼したところ、評価の2割でしか売れないと言われて、相続税が払えないと嘆いておられました。当社の取引先ではその価格の3倍以上で購入するところがあり、相続税が払えるめどはつけられました。こうした事実からは、銀行は知らないお客様にこれでしか売れないと言って安く買い取り、転売益を得ているのでは?自分たちの利益ありきで、お客様目線ではないと感じます。相続や不動産など財産のことは、誰に頼むかにより結果が変わることもあるため、慎重に選んで進めましょう。
Vol.35 二世帯住宅は区分登記せずに特例を生かす(2023.06)
相続を取り巻く現状についてのアンケートで、『親または子と相続の話をしたことがありますか?』という問いに6割以上の方がしていない回答されています。核家族化が進んでいるため、“生前対策”をしていない人がほとんどという結果がでており、なぜ、相続トラブルに発展するのかということの理由が如実に表れています。 つぎに『親または子と相続の話をしない理由は何ですか?』の問いには親子で相続の話をしたことがないという人が6割という結果。親世代は「話すほどの資産はないと思っている」ことがわかり、子ども世代は「親には話しづらい」と回答しています。 いずれにしても「対策ができていないから相続トラブルになる」ということが見えてきます。質問項目ですが、皆さまの答えはいかがでしょう?相続で家族間の争いとなり後悔しないためには親子で協力して親が元気なうちから家族で話をしておくことが必要なのです。
Vol.34 「遺留分」算定は―土地全部で(2023.05)
Тさん(60代女性)は3姉妹の長女で父親と同居。父親は家を残してもらいたいと遺言書でTさんに相続させました。ずっと同居してきたことで家をTさんが相続するのは自然な流れでしたが、なにも相続するものがない妹二人から遺留分請求が起こされました。 自宅は100坪あり、大きな家が建つ邸宅で建売住宅の3倍もあります。 父親の財産に預金はほとんどなく、土地の一部を売って遺留分を捻出するにも、引っ越しして建物を解体しないと売れません。しかも土地の一部を売るだけでは遺留分の算定が難しくなり、調停や裁判に時間がかかるのです。しかし、土地を全部売却すると「時価」が決まり、「遺留分」も算出できるため、全部の売却を決断されました。父親の「家を残してほしい」という希望は実現しませんが、妹二人に遺留分として父親の財産を渡すのは当然のこと。住み替えが心機一転になるTさんは話しておられます。
Vol.33 認知症になる前に(2023.4)
Hさん(50代女性)一人娘。父親は70代で亡くなり、母親が一人暮らから80代半ばには歩くことが大変となり、介護施設に入所されました。それからあっという間に2年が経ち、実家の空き家の管理も気になり始めました。Hさんから母親の状態を聞いた当社は、母親の意思が確認できるうちに、すぐ売却したほうがいいとアドバイスしました。介護施設に入所すると認知症が一挙に進行してしまう方もあり、売却は早い方がいいと判断したのです。これを先延ばししてしまうと介護費用が足りなくなり、自宅を売却しようとしても、母親の意思確認ができず、名前を書くこともできないときは売れなくなるのです。母親の意思確認もでき、お仏壇や位牌を供養し、荷物の処分などして、家の売却は無事に終わり、住まない家が現金に変わりました。これからまだ長い介護に費用がかかっても不安がなくなったと安心されました。
Vol.32 親子、家族がキーワードく(2023.2)
親が死ぬ前に、家族とやりたい10のこと」(共著・クロスメディア)は親子で考える相続の本。また「親が元気なあいだに子どもがヒアリングしながら書く相続ノート」(監修・秀和システム)は子どもが親にヒアリングしながら活用するノート。ともに親子、家族がキーワードとなっています。 その背景として、親子で話す機会が減っていて家族で意思の疎通がとれない現実があるからです。そうした家族関係が相続トラブルを引き起こし、手続きも難航して大変なことになりかねません。両書とも、これからの時代に必要なコンセプトだと共感し、執筆、監修をさせて頂きました。 当然、様々な家族があり、活用の仕方も取り組み方もおひとりずつ違うことでしょう。 この本やノートを活用して、親子で気持ちを共有したり、確認したりする機会を持って頂くことを願っております。夢相続もサポートさせて頂きますのでご相談下さい。
Vol.31 土地の共有を分けるのに費用がかかる!(2023.1)
Nさん(70代・女性)きょうだいはひとつの敷地に自分たちの家を建てて住んできました。母親と長男家族が住む家が角地で80坪、真ん中が長女家族で50坪、左角には次男家族で50坪。父親が亡くなった時には母親と子供たちが法定割合で相続し、そのまま土地全体を共有しました。母親が亡くなった時に、いよいよ分けようと利用に合わせて土地を分筆して、共有を解消、単独名義にすることになりましたが、分筆せずに全体を共有していたばかりに、共有解消の等価交換が必要となり、分筆、交換登記に余分な費用がかかってしまったのです。 等価で交換できると交換差益の譲渡税はかかりませんが、登記費用が倍上も余分にかかり、他に測量、分筆などの費用がかかります。家を建てるときから分筆して、共有せずに、単独で相続することが望ましかったと言えますので、土地の共有はしないほうが賢明でしょう。