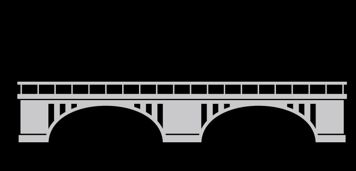日本橋モラロジー事務所からの大切なお知らせです
新年明けましたおめでとうございます。皆様のご健康をお祈り申し上げます。
日本橋モラロジー事務所代表世話人 大久保章
.jpg)
代表世話人のコラム
令和8年1月『丙午』
いよいよ令和8年がスタート。今年は午年。特に干支の43番目の丙午の年。「丙」と「午」どちらも火の性質を持つことから、丙午は火の力を象徴する年とされているそうです。馬にまつわる話題で、日本では馬は神の使いとしても大切にされてきました。馬は「神様の乗り物」であり、生きた馬を神社に奉納する風習が奈良時代から存在していたそうです。奉納された馬は「神馬」とよばれ、今も神事などで使われています。皇居は勿論、伊勢神宮にもモラロジー教育財団にも馬が飼われています。また、馬の絵を木の板に描いて奉納したのが「絵馬」のはじまりだといわれています。日本人にとって馬は神聖で、ご利益のある生き物としても大切にされてきたことがわかります。もう一つは、「馬」という漢字を横方向に反転した「左馬(ひだりうま)」という縁起物のモチーフがあります。「うま」という言葉をひっくり返すと「まう(舞う)」になり、おめでたさを連想させるため縁起が良いのだそうです。なかでも将棋の駒に反転した「馬」の字を書いた「飾り駒」が代表的な左馬として有名です。左馬は、つぎのような幸運を招くといわれています。商売繁盛で「人が馬を引いてくる」が逆転し「馬が人を引いてくる」から万事が順調にいくという意味に繋がる。モラロジーでもよく使われる故事に「人間万事塞翁が馬」があります。昔、中国北方の塞の近くに住む老人の馬が塞の外に逃げてしまいました。人々がなぐさめると、老人は、「そのうちに福が来る」と答えます。やがて、逃げた馬はすばらしい馬を連れて帰ってきました。人々が祝うと、今度は「これは災いのもとになる」と語ります。そして、老人の息子がその馬に乗ったところ、落馬して足を折ってしまいます。人々が見舞うと、老人は、「これが幸いのもとになるだろう」と答えます。1年後に戦争となり、若者たちはほとんど戦死しましましたが、老人の息子だけは足が不自由だったために兵役をまぬがれ、死なずにすんだ。一見不幸に思える出来事が、実は幸運につながることもある。目先の出来事に一喜一憂しないで大きな視点を持つことが大事という戒めです。新しい年、自分の目で大きな視点で物事を判断し、自らの標準をもって行動しようと思います。
令和7年12月『諸橋轍次』
父(定七)が残した書籍の中の諸橋轍次著「誠は天の道」を私の勉強会(オリーブの会)で資料として使用したところ、参加者のお一人から諸橋先生は「大学の時にずいぶん勉強しました」とお話しいただきました。そんなことで、諸橋 轍次を調べてみました。諸橋 轍次 明治(明治16年-昭和57年)は、日本の漢学者で大正十五年から大漢和辞典を編集に携わる。学位は文学博士。なぜか上記の書籍は昭和五十四年廣池学園事業部発行で、昭和四十一年国立教育会館で行われた講演会の転載の内容。また、「古典のかがみ論語三十三章」も学園から発刊されていました。廣池千九郎は恩師より文学博士より法学博士を目指すように指導され大正元年に法学博士、昭和四年に文学博士になった諸橋先生とはいろいろな研究という意味でかなり重なっていると感じました。廣池千九郎は法学を極めたことでモラロジーに繋がり、諸橋轍次は漢学を極めたということ。モラロジーの中心的な考え方は両者とも同じだと感じました。上記の本には「誠」(中庸)の解説から「自誠明、謂之教(明らかなる自(よ)りして誠なる、これを教えと謂う)」という人間修養について書かれています。誠ということを積極的にやっていくと自ずから物事の道理が明らかになり、これを誠なるを教えという。つまり、学問や経験によって万象に流れる天理を明らかにすることによって人生をつかむことができ、これを教えということ。まさにモラロジーの考え方の本であり、学園が発行した理由だと感じました。諸橋轍次の名言に「学ぶには大道があります。それを通らずに小道を歩いていくと、必ず行き詰まりがあり、もとへ戻らなくてはいけなくなります。ところが奇をてらう人間とか、世間の評判を得ようというような人間は、小道を行くのです。名前を早く売るには都合がいいからでしょう。しかし小道を行った人間は決して大成しません。学問だけでなく何事においてもそうです。」上記の本の内容には「誠は天の道」と書かれていて、この大道も天の道という意味を表していると思います。道徳科学の論文では大道を公道と著しています。大道、公道、自然の法則の中の一部として生きている人間。天理を理解することが人間修養の大事なところと理解しました。
令和7年11月『誰かを幸せにできること』
私は大の小田和正ファンでオフコース時代からレコード・CDを集め、ツアーがあると必ずコンサートに行っています。今年も2回コンサートに行き感激しました。いつもコンサート中、とても幸せな気持ちになります。時間を忘れ胸いっぱいの時を過ごさせていただいています。小田さんのCD、So far so goodの歌詞「春がまたここに帰って来た やわらかな風が街を包んだ 今すべてのことが変わっていく 人の心も変えていく 嬉しいこと悔しいこと繰り返しながら相変わらずの毎日 そんな自分だけど誰かを幸せにできるとしたら きっとそれが一番幸せなこと 小さな夢と不安を抱えて自分が思う道を歩いている たとえ選んだ道が間違っていても無駄な時間が流れるわけじゃない どれだけ遠回りになったとしてもいつか目指したその場所へたどり着けるはず でも誰かを幸せにできるとしたら きっとそれが一番幸せなこと 春が来て春が行く 生きて行ければまた時は来る 誰かを幸せにできるとしたら きっとそれが一番幸せなこと この街にまた春が帰って来た 少しだけ強く今風が吹いた」この歌を聴いていると小田さんの思いがすごく伝わってきます。モラロジーを学んでいなければこの深さはきっとわからなかったと思います。さて、10月3日から畑毛記念館の千九郎研究講座を受講しました。畑毛に行く理由の一つが、山本幾雄講師からの助言です。休憩時間のほんの数分の会話の中に示唆を頂く言葉があります。今回は幾雄さんから「今年はセミナーの出講はあるのか」と聞かれ「いつも秋にあるのですが今年はありませんでした。きっと若い講師が出講するのだと思います」すると「若い講師は体験がない。開発救済(人の道徳心を引き出す)をしていないからいい講義が出来ない」とご指導いただき、おっしゃる通りと私もうなずきました。道徳心、思いやりの心が大きくなれば人は幸せになる。このことは「誰かを幸せにできるとしたら、きっとそれが一番幸せなこと」それを実行するのがモロジーを学ぶ私達。78歳でもまだ頑張っている小田さんの歌を聴くと、まだまだ頑張ろうという気持ちになりました。
令和7年10月『無慈悲の慈悲』
以前、高校の部活指導で練習試合を行ったとき、若い先生から部員についての相談が合った。2年生の生徒とその親から指導が厳しいという指摘を受けたそうです。そしてその生徒数名は退部したそうです。その対応について私は無慈悲の慈悲のお話をしました。薬師寺故高田後胤前管主は師匠である橋本凝胤が非常に厳しく、いつもこっぴどく叱られたそうです。ところが、戦時中高田前管主が野戦砲兵学校に入隊した際に師匠から週に二三通の書簡を頂いたそうです。そういう師匠は確かに厳しい人でしたが、その厳しさは師匠の弟子への厳しい愛情であったことが後になって分かったそうです。そのときに高田前管主は無慈悲の慈悲を感じたそうです。古文真宝に「子を養いて教えざるは父の過ちなり。訓導して厳ならざるは師の惰(おこた)りなり。父教え師厳なること両つ(ふたつ)ながら外無けれども 学問成ること無きは子の罪なり(子供を生んでも躾をちゃんとしなければ父親の過まちである。教え導くのに厳しくしないのは師の怠たりである。父は教え、師は厳しく、両者ともに一意専心、不足をいう余地もないのに、学問が成就しないのは、勉強しない子の罪である。)」とあります。父親がきちんと教え、師が厳しく指導する。そこには無慈悲の慈悲がなければならないと思います。また、今は個性尊重と言われ、子どもの個性だからそれを伸ばしてあげるのが親なんだとばかり何も訓練しない、意見もしない、躾もしない、何もしないで放ったらかし。本来は訓練によって磨き出されるのが個性で、自分の姿をもって子供の個性を磨いてあげるための訓練や躾を怠りなく勤めていくことが大切だと後胤前管主はおっしゃっています。あるときには父親が理不尽なことを言うかもしれません。指導者が納得のいかないことをさせるかもしれません。ただ、そこにきちんとした慈悲があれば子供は成長していくはずです。今の世の中はパワハラだモラハラだと訴える人たちがいます。確かにハラスメントをしている人もいると思います。しかし、その訴えている人たちは父親や師が慈悲をもっていっていると感じることはないのでしょうか?
令和7年9月『目に見えないお陰や過ちに心を向ける』
戦後80年。モラロジー財団の青年部が6月21日から沖縄で開催された青年研修会に参加。初日にジャーナリストの三荻祥氏の特別講話をお聞きしたそうです。その講演の中で三荻氏は沖縄戦についていろいろなガイドブックを調べたが、『犠牲になった沖縄』という見方しかないと指摘し、自身も当初かわいそうな沖縄という印象を持ったそうです。しかし、ひめゆり学徒隊などの遺書や手記を読み進めるうちに見方が変化したそうです。沖縄戦で県民はただ犠牲になったということはない。故郷である沖縄を守るために軍・官・民が一体となって懸命に戦ったと説明された。また、沖縄の歴史を正しく伝えるためにどうしたらいいかという質問に対して、八十年間の犠牲者史観が染みついていると指摘したそうです。私も現職の時、飛行機での修学旅行が解禁になり、すぐに沖縄修学旅行に行きました。平和教育という目的だったので平和の礎やガマ(洞窟)に入り案内の方のお話をお聞きました。ガマの中は照明 のない自然のままの洞窟で懐中電灯を持って入り、奥に入ると懐中電灯を消し真っ暗の中でお話を聞きました。まさにここが負傷兵のいた場所でひめゆり学徒隊が傷病兵のお世話をした所。そして、そのひめゆり学徒隊の自決のお話をお聞きしました。3年目の修学旅行でお話をお聞きしたときに、まさにこの犠牲者史観を強く感じました。さて、昭和60年瑞浪麗澤高校創立25周年記念講演会で薬師寺故高田後胤前管主がお話しされました。その中で「今日の日本の平和と繁栄について。あの大東亜戦争の時に、310万人を超えた方々がお隠れになっています。あのお命のご遺産が、今日の日本の平和である、繫栄であるということをどうぞお忘れにならないようにお願いします。過去のお陰を不真面目にして、家であれ、国であれ、個人の人生であれ、未来豊かに栄えた例はございません。戦争に行かれた方々だって、なにも自分の名誉や利益のために戦争に行かれたわけではありません。個人個人の行為、個人個人の業(心づかい、心がまえから発する行為)というものがあり、国民であるがゆえの業や、地域社会に住む人々の共通の業、共豪というものがあります。私どもに代わって、それらの所感を背負って亡くなられた、その310万人のお命のご遺産が今日の日本の平和である、繁栄であるということを忘れてはならないと思います。けれども私ども今日、果たしてそういうお命に対して申し訳の立つような生き方ができているでしょうか。私も人様の前でお話しさせて頂く時には、最もらしいことを申しますが、自分自身に立ち戻った時、忸怩たらざるを得ない、本当に申し訳さをお詫びしないではいられません。そいうことを思いながら、毎年、慰霊法要の旅にあがらせて頂いております。サイパンン島にしてもグアム島にしても、今は海水浴や観光に行くことができます。これは、やはり戦後の平和と繁栄のお陰です。けれども、そういう所に行った人たちの姿を見ていると、無知なるがゆえの罪の恐ろしさを思わずにはいられんことが常です。ちょうどジャングルへ入ってそこでお経をあげていると、目の前にご遺骨がある。こういう島の周辺に飛行機や船が無数に沈んでいます。そういうことを思うにつけて、無知なるがゆえの罪の恐ろしさを感じます。」日本橋事務所は9月13日に靖国神社に正式参拝をします。目に見えないお陰に改めて感謝の気持ちを持っていきます。
令和7年8月『新盆』
私は次男の末っ子であまり仏事に関心がなく今日まで来ました。ところが、全号記述したように私の両親・義父母・義妹が亡くなっていくとそんなわけにはいかなくなりました。今年は義妹が亡くなっての新盆。我が家では初めて法要の準備を考えなければなりません。お供え物・盆棚の飾りを葬儀社さんにお願いして妻が準備しています。そして、法要について平井宥慶の「弘法大師に学ぶ」を読んで気が付きました。法要の趣旨を述べられているのが「願文」だそうです。願文とは仏さまに願う文章で私たちの想いを表したものだそうです。願文には①仏さまに讃えて帰依(心のよりどころ)する心を表明する②今地上の人々への敬いの想いを吐露する。つまり、モラロジーの考えである伝統に対する恩の深さと同じであり、親の恩は身を粉にしても報じ難しと言われます。③法要する両親・義父母・義妹への思い出、悲しみを述べ喪失感を吐露する。妻は先立たれた義妹に対してまだまだ悲しみを抱えているようです。その思いを吐き出すのが今回の法要の意味かもしれません。④自分がどのように“いま”を生むかえているかを述べる。つまり、普段の自分の不徳を反省すべく法事を施し、功徳を願うということ。単に迎え火をして先祖の霊が留まり、送り火をして帰ってもらうというような安易な気持ちではいけないことを知りました。⑤その決意を、何らかの行動を為すことで補い、救いいただけるように祈願する。私自身の毎日の生活を振り返り、心を付けた道徳実行を再度決意することではないかと思います。⑥理想に近づいていればよく、そうでなくても神仏に力を借りて明日への活きる元気を頂けるようにお願いする。つまり、世界の平和と明日の自分とそのご縁の人々の安心と元気を祈願すること。以上がお盆の法要の意味だそうです。先祖の霊が滞在しているしるしである盆提灯を準備し、迎え火をする中で自分の不徳を反省し人様のお役に立つ人間になるよう努力することを誓う。今年の7月13日の迎え火に際して、改めて今までの自分の人生とこれからの人生を考える機会にしようと思います。
令和7年7月『星野家具足』
6月1日(水)モラロジー教育財団伝統の日に参加しました。モラロジーでは伝統本位という考え方なので、たくさんの方々が参加して行事が開催されました。家の伝統では親・祖先を大切にするということを教えられています。さて、1月2日に義妹が他界しました。義母が一昨年の11月に義父が2010年に他界しました。姉妹二人でしたが妹に先立たれ、妻は結構ショックの様です。今まで我が家の仏壇には生の仏花はあまり置いていませんでしたが、草月流の師範の義妹なのでお花を大事に飾っています。そして、妻の実家の仏壇を片付けることになりました。何とお位牌が10基あり、古くは安政5年のお位牌でした。そして、そのお位牌にも驚きましたが、実家には具足がありました。私がまだ結婚する前に妻の自宅に呼ばれたのがゴールデンウィーク頃で、玄関にその具足が飾られていました。当時は玄関にある具足より、義父に遭うことで緊張していて目に入りませんでした。この具足も片付けることになり、調べてみると大阪の高槻藩の文字が書かれていました。今回、改めて妻の実家の伝統に驚くばかりでした。以前から妻の運の良さに感心していましたが、ここにその原因があるのだと実感しました。廣池千九郎学祖の教えと同じですが、安岡正篤先生の傳家寶七項目の2項がこんな内容でした。「一、我が幸福は祖先の遺恵。子孫の禍福は、我が平生の所行にある。二、平生己を省み、過ちを改め、事理を正し、恩義を厚くすべし。百薬も一心の安きに如かず。」妻の幸福は祖先の遺恵にある。結婚40年を過ぎそばにいる私は、妻の好運命に驚くばかりです。一言で言ってしまえば運がいいと言いますが、本当に驚くことばかりです。なので、そういう時は「ママだから」当然だと片付けています。この運の良さこそ祖先の遺恵から来るものなのだと、星野家の最後を見て感じました。本当に自分たちの善因が善果になることを実感しております。そして、子孫の禍福は普段の私の行いと心づかいが大切で、百薬もかなわないということ。子供や孫のために善行をただ重ねるのみとして実行しています。
令和7年6月『無党無偏』
5月6日のモラロジー道徳教育財団記念館講話に井出元副理事長の講話をお聞きしました。財団の麗澤館玄関の正面に掲げられている、博士の最初の教えである「無党無偏天道平平」のお話をされました。無偏無党とは、主義や思想にこだわることなく、一定の党に所属せずに、公平で中立の立場をとること。廣池博士は日清日露戦争、第一次世界大戦、また政治政党立ち上がった戦前・戦中・戦後を通して首尾一貫してこの基本的姿勢を守り通しました。無党無偏は団体の生き方であり、個人の生き方でもあります。さて、個人として私たち自身に主義主張にこだわらず公平でいることをどう考えるか。私は般若心経が頭に浮かびました。「摩訶般若波羅蜜多心経」とは偉大なる真理に目覚める智慧で、安らぎの世界に至るための、仏教の心髄となる教えです。「般若」とは悟りの智慧という意味で、知恵とは人間の知恵で難しい状況を乗り越える知恵。智慧は物事を正しくとらえ、真理を見極める為の認識能力。心経の中にある「色即是空 空即是色」とは一言で言えば「空」という一文字が般若心経の心と故高田好胤薬師寺管主・法相宗管長がおっしゃっていました。「空」とは「むなしい」「そらぞらしい」「からっぽ」という意味がありますが、心経では「かたよらない」「とらわれない」という意味を表しています。そして、好胤管主は般若心経の心を「偏らない心・こだわらない心・とらわれない心・広く広くもっと広くそれが空の心なり」とお話しされています。私はこの「偏らない心・こだわらない心・とらわれない心」を自分の標準として心の中心に置いています。そうすると物事にこだわらない、とらわれないことが多くなり不安や悩みが無くなりました。自分の目でみて、耳で聞いたことをきちんと判断し、他に惑わされることなく自分の道を行くことができるようになりました。明治天皇のお歌に「あさみどり澄みわたりたる大空の広きをおのが心ともがな」。すべての人の心、すべての価値を受け入れる、広々と澄みきった心を歌われています。まさに「空」の心だと思います。少しでもこの「空」の心に近づけたらと思います。
令和7年5月『陰徳について』
4月の感謝の集いのお当番に来て頂いた鈴木広英講師が道徳的共同体づくりに何ができるのか、知恵を集める時で次回参加者で話し合いをしようということになりました。さて、現在にわが国は道徳的共同体ではないのでしょうか。私はヤフーニュースやMSN(マイクロソフト)ニュースを毎日見ます。必ず見るのが訪日外国人たちのわが国に対する感想です。街がきれいで静か。人がやさしく親切。食べ物がおいしい。交通手段も時刻に正確で便利等。まさに日本が誇る道徳的共同体に対する感想ではないでしょか。しかし、その自覚がマスコミの影響で薄らいでいる気がします。夕方見るニュースは高齢者の運転事故、逆走。特殊詐欺事件や無人店舗での窃盗。殺人事件等の不道徳な内容ばかり。人が行った良いことや道徳的なことはニュースにならないようです。マスコミが日本人を貶めているといっても過言ではない気がします。3月25日に能登輪島に行ってきました。昨年の地震後何かお手伝いができないかと思っていましたが、我が家に不幸が続きできませんでした。やっと時間が取れたので経済支援と思い行きました。震災当時に美しの森幼稚園が支援を行った輪島の海の星幼稚園に義援金をお持ちすることが目的の一つでした。宿泊した山中温泉から車で3時間。海の星幼稚園に着くと、前に走っていた車からお米を幼稚園に運び入れていました。輪島にお米を持ってきたそうで、そのうちの30kg2袋を幼稚園に置いていきました。日本人は善いことをしてもそれを自慢しない。陰徳を積むことをよしという考えの方が多いと思います。令和3年の日本橋だよりに「陰徳を積む」を書きましたが、道徳的共同体を考える時、個々人がコツコツと陰徳を積む。モラロジーHPのブログに『心の内からわき起こる動機にもとづく「陰徳」は、報酬や評価では得られない深い喜びや充実感をもたらします。また、自分の利益や名声を目的とせず、人や社会のためにすすんで行動する姿勢は、周囲にポジティブな影響を与えます。』つまり、人知れず行う道徳実行は、自分の中に充実感が湧き、道徳的共同体づくりに貢献できるのだと感じています。
令和7年4月『街の品位を高める』
毎朝モラロジアンの先輩が近所のごみを拾い掃除をしています。私も掃除をしたほうが良いのですが、なかなか仕事を続けていると真似ができません。松下幸之助氏の商売心得帳の中に「街の品位を高める」という著述があります。自分のお店を常にきれいにしてお客様が入りやすくすることが商売が発展していくために大事な一つ。そして、店舗をきれいにするということは単にお客様の購買意欲を高めるためだけでなく、自分の街の一部をなす店舗であるから街の美醜に影響を与えると書かれています。お店や家々が街全体を考えるということは、その街の道徳心にも繋がっていると思います。2月から我が家の外壁の塗装をお願いしています。さて、屋根と壁の色をどうしようか。息子たちが我が家に来た時に相談しました。すると、息子と孫娘は屋上に行き周りの家を見まわして、屋根と壁の色を決めてきました。なんでその色にしたかを聞くと周りの家々と違和感のない色にした。家は街の一部で、周囲になじむことを考えたということです。それを誰が言うでもなく決められることに、我が子ながら感心しました。40年間の都立高校教員生活で、勤務場所は城東地区(墨田区・江戸川区・葛飾区)でした。高校に勤務していたので地区の中学校の様子が耳に入ってきます。生活指導をしていたからなおさら問題行動が多発している中学校は気になっていました。当然、荒れている中学校の地域・コミュニティの道徳心がそこにないと感じていました。息子家族が孫のアレルギーの関係で家を出る際、どこに住むかはこの様子が頭にあり息子夫婦に伝えました。2か所の候補がありましたが、現在住んでいる柴又を進めました。帝釈天があり昔からの住民がしっかり地域を支えている様子を感じたからです。その孫たちも下の孫が無事小学校を卒業。お嫁さんは柴又の地域性に感謝しています。そういう意味で、両国も同様でお相撲さんの街、地元の人たちが代々住んでいる町。安心して生活できています。地域社会での人のつながりが薄れてきている現在、まず自分の住んでいる地域・コミュニティを自分自身が大事にすることが重要と思うようになりました。
令和7年3月『自衛隊に感謝』
先日、モラロジー道徳教育財団の服部道雄参与より公益財団法人日本国防協会編集の『日本の国防』に執筆された「松島基地ブルーインパルス研修」の文章を頂きました。服部参与には日本橋事務所の先輩から日本橋だよりを送っていただいており、その縁で私に送っていただきました。掲載された内容は日本国防協会の意義・役割、気付かずとも守られている幸せ(日本の領空を侵犯する不審機は令和5年は669回、平成28年は1168回。雨の日も、風の日も、盆も正月も、命令があれば5分以内にスクランブル発進できるよう身構えて下さっている隊員のおかげ)、最大の被害地石巻市にある「みやぎ東日本大震災津波伝承館という内容等です。その「みやぎ東日本大震災津波伝承館」の中に、福島原発事故後3月17日に宮城県の霞目飛行場から飛び立ったヘリコプターが原子炉上空からバスケットの水を投下したこと。この時、隊員は重さ20キロの鉛の防護衣を装着していたことが掲載されていました。私は東日本大震災時における自衛隊の活動は忘れることができません。3月11日後の5月ゴールデンウィークに日本橋事務所の皆様と支援に行きました。岩沼の海岸に向かって車を走らせた時、自衛隊員3名がブルーシートを引きずって重い足取りで歩いている姿は忘れられない光景です。翌日、避難所の前で避難者に豚汁やコーヒーをお出しした際、近くに避難者への食事を提供すらために若い自衛隊員がいたのでコーヒーをお出ししました。後で師団長様からご丁寧なお礼のお手紙をいただきました。当時、隊員の中にPTSDになった隊員がいたという話を聞きました。『現在、自衛隊に入ってくる若者は、特別な人ではありません。中には挨拶もできず礼儀も知らない若者もいます。しかし、一年間教育するとすばらしい隊員になります。どのような教育をするかといえば、入隊した日から「公」とか「国家」ということを大上段から教えるのです。「私」とか「個」のみの教育を受けてきた彼らは、大きなカルチャーショックを受けます・しかし、国を守ることがいかに尊いかを知り、災害派遣で一度でも人の命を救う経験をすると、皆一様に変わります。公に尽くすことは心地よく、誰が何と言おうと人間の幸せだからです。私は部下に常々「人は人によって生かされ。人は人のために生きる」と話してきました。若者が国を守ることの崇高さ、人を守ることの心地良さ、そして実際に人を助けるという体験をすると人が変わります。(織田郁夫 まなびとぴあ8月号)』2月4日日本海側を中心に大雪が予想されることを受け、中谷防衛大臣は災害に備え初動対応にあたる部隊「ファスト・フォース」を24時間待機させるなど「万全を期す」と強調しました。私たちは自衛隊の存在をなかなか意識することができません。しかし、もっと自衛隊の隊員への感謝をしなければと思いました。
令和7年2月『お書初め』
小学校ではお書初めがありました。お書初めは平安時代の宮中における「吉書の奏(きっしょのそう)」という行事がルーツだそうです。吉書の奏は、改元・代替わり・年始など、ものごとがあらたまった節目に、天皇に文書を奏上するというもの。日本人としては大事な行事でした。私の両親・義理の両親とも達筆で毎号に筆絵を載せていただいています。そして、私も少し字がうまくなればと思い高校勤務の時に空いた時間に生徒と一緒に書道の授業を何年か受けました。小学生の時に少し書道教室に通いましたので違和感なく筆を持ちました。その後、練習のつもりで年賀状の宛名書き等にも筆を持ちました。今回小学生のお習字を見て2度書きをする子供達に驚きました。子供達には「お絵描きじゃないんだから」と言って見回りました。時間割にも書写と書いてあるクラスもあり私の書道のイメージと少し違うと感じました。書写とは文字を正しく整えて一字ずつ書き写すことで、小・中学校の国語の授業の一部として習います。 毛筆や硬筆を用いてお手本どおりに文字を正確に書き写し、誰が見ても美しい字を書けるようにすることが目標です。 目的や必要に応じて速く文字を書く力も養う。習字は文字通りに字を習うことを指し、字の正しい書き順や美しい字の書き方を習う。書道は字を通した自己表現が最大の目的。 文字が生み出す美しさを追求することが書道の定義・目的ということ。子供たちを見ていて文字を正しく整えるという意味であれば2度書きや小筆でなぞることもありかなと思うようになりました。以前の日本橋だよりに不易と流行をテーマにしました。『不易ふえきを知らざれば基立ちがたく、流行を知らざれば風新たならず。』不易ふえきすなわち、変えてはならない伝統やしきたりを知らなければ、基礎が成り立たない。しかし、流行すなわち時代の変化に沿った新しさも知らなければ、新たなものは生まれない。古い修身の教えも理解したうえで、時代に合った新しい道徳も納得しなければとお書初めを見て感じました。