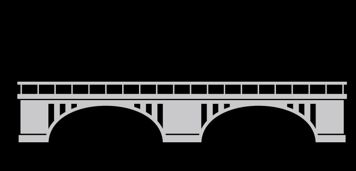日本橋モラロジー事務所からの大切なお知らせです
令和7年度伝統の日
6月1日(水)モラロジー教育財団伝統の日に参加しました。令和8年に100周年になる財団です。廣池幹堂理事長の挨拶の中で「人から求められる人」というワードが私の中で残りました。一般的には社会では「人間力」のある人。 AIに聞いてみると人間力とは、日本でよく使われる言葉で、簡単に言えば「人としての総合的な力」や「人間としての魅力・信頼性・行動力」などをさす、という答えでした。モラロジーではその人の品性ではないかとおみます。自分の品性を上げて人から求められる人を目指したいものです。

モラロジー教育財団のマスコット モラちゃんです。
代表世話人のコラム
令和7年4月『街の品位を高める』
毎朝モラロジアンの先輩が近所のごみを拾い掃除をしています。私も掃除をしたほうが良いのですが、なかなか仕事を続けていると真似ができません。松下幸之助氏の商売心得帳の中に「街の品位を高める」という著述があります。自分のお店を常にきれいにしてお客様が入りやすくすることが商売が発展していくために大事な一つ。そして、店舗をきれいにするということは単にお客様の購買意欲を高めるためだけでなく、自分の街の一部をなす店舗であるから街の美醜に影響を与えると書かれています。お店や家々が街全体を考えるということは、その街の道徳心にも繋がっていると思います。2月から我が家の外壁の塗装をお願いしています。さて、屋根と壁の色をどうしようか。息子たちが我が家に来た時に相談しました。すると、息子と孫娘は屋上に行き周りの家を見まわして、屋根と壁の色を決めてきました。なんでその色にしたかを聞くと周りの家々と違和感のない色にした。家は街の一部で、周囲になじむことを考えたということです。それを誰が言うでもなく決められることに、我が子ながら感心しました。40年間の都立高校教員生活で、勤務場所は城東地区(墨田区・江戸川区・葛飾区)でした。高校に勤務していたので地区の中学校の様子が耳に入ってきます。生活指導をしていたからなおさら問題行動が多発している中学校は気になっていました。当然、荒れている中学校の地域・コミュニティの道徳心がそこにないと感じていました。息子家族が孫のアレルギーの関係で家を出る際、どこに住むかはこの様子が頭にあり息子夫婦に伝えました。2か所の候補がありましたが、現在住んでいる柴又を進めました。帝釈天があり昔からの住民がしっかり地域を支えている様子を感じたからです。その孫たちも下の孫が無事小学校を卒業。お嫁さんは柴又の地域性に感謝しています。そういう意味で、両国も同様でお相撲さんの街、地元の人たちが代々住んでいる町。安心して生活できています。地域社会での人のつながりが薄れてきている現在、まず自分の住んでいる地域・コミュニティを自分自身が大事にすることが重要と思うようになりました。
令和7年3月『自衛隊に感謝』
先日、モラロジー道徳教育財団の服部道雄参与より公益財団法人日本国防協会編集の『日本の国防』に執筆された「松島基地ブルーインパルス研修」の文章を頂きました。服部参与には日本橋事務所の先輩から日本橋だよりを送っていただいており、その縁で私に送っていただきました。掲載された内容は日本国防協会の意義・役割、気付かずとも守られている幸せ(日本の領空を侵犯する不審機は令和5年は669回、平成28年は1168回。雨の日も、風の日も、盆も正月も、命令があれば5分以内にスクランブル発進できるよう身構えて下さっている隊員のおかげ)、最大の被害地石巻市にある「みやぎ東日本大震災津波伝承館という内容等です。その「みやぎ東日本大震災津波伝承館」の中に、福島原発事故後3月17日に宮城県の霞目飛行場から飛び立ったヘリコプターが原子炉上空からバスケットの水を投下したこと。この時、隊員は重さ20キロの鉛の防護衣を装着していたことが掲載されていました。私は東日本大震災時における自衛隊の活動は忘れることができません。3月11日後の5月ゴールデンウィークに日本橋事務所の皆様と支援に行きました。岩沼の海岸に向かって車を走らせた時、自衛隊員3名がブルーシートを引きずって重い足取りで歩いている姿は忘れられない光景です。翌日、避難所の前で避難者に豚汁やコーヒーをお出しした際、近くに避難者への食事を提供すらために若い自衛隊員がいたのでコーヒーをお出ししました。後で師団長様からご丁寧なお礼のお手紙をいただきました。当時、隊員の中にPTSDになった隊員がいたという話を聞きました。『現在、自衛隊に入ってくる若者は、特別な人ではありません。中には挨拶もできず礼儀も知らない若者もいます。しかし、一年間教育するとすばらしい隊員になります。どのような教育をするかといえば、入隊した日から「公」とか「国家」ということを大上段から教えるのです。「私」とか「個」のみの教育を受けてきた彼らは、大きなカルチャーショックを受けます・しかし、国を守ることがいかに尊いかを知り、災害派遣で一度でも人の命を救う経験をすると、皆一様に変わります。公に尽くすことは心地よく、誰が何と言おうと人間の幸せだからです。私は部下に常々「人は人によって生かされ。人は人のために生きる」と話してきました。若者が国を守ることの崇高さ、人を守ることの心地良さ、そして実際に人を助けるという体験をすると人が変わります。(織田郁夫 まなびとぴあ8月号)』2月4日日本海側を中心に大雪が予想されることを受け、中谷防衛大臣は災害に備え初動対応にあたる部隊「ファスト・フォース」を24時間待機させるなど「万全を期す」と強調しました。私たちは自衛隊の存在をなかなか意識することができません。しかし、もっと自衛隊の隊員への感謝をしなければと思いました。
令和7年2月『お書初め』
小学校ではお書初めがありました。お書初めは平安時代の宮中における「吉書の奏(きっしょのそう)」という行事がルーツだそうです。吉書の奏は、改元・代替わり・年始など、ものごとがあらたまった節目に、天皇に文書を奏上するというもの。日本人としては大事な行事でした。私の両親・義理の両親とも達筆で毎号に筆絵を載せていただいています。そして、私も少し字がうまくなればと思い高校勤務の時に空いた時間に生徒と一緒に書道の授業を何年か受けました。小学生の時に少し書道教室に通いましたので違和感なく筆を持ちました。その後、練習のつもりで年賀状の宛名書き等にも筆を持ちました。今回小学生のお習字を見て2度書きをする子供達に驚きました。子供達には「お絵描きじゃないんだから」と言って見回りました。時間割にも書写と書いてあるクラスもあり私の書道のイメージと少し違うと感じました。書写とは文字を正しく整えて一字ずつ書き写すことで、小・中学校の国語の授業の一部として習います。 毛筆や硬筆を用いてお手本どおりに文字を正確に書き写し、誰が見ても美しい字を書けるようにすることが目標です。 目的や必要に応じて速く文字を書く力も養う。習字は文字通りに字を習うことを指し、字の正しい書き順や美しい字の書き方を習う。書道は字を通した自己表現が最大の目的。 文字が生み出す美しさを追求することが書道の定義・目的ということ。子供たちを見ていて文字を正しく整えるという意味であれば2度書きや小筆でなぞることもありかなと思うようになりました。以前の日本橋だよりに不易と流行をテーマにしました。『不易ふえきを知らざれば基立ちがたく、流行を知らざれば風新たならず。』不易ふえきすなわち、変えてはならない伝統やしきたりを知らなければ、基礎が成り立たない。しかし、流行すなわち時代の変化に沿った新しさも知らなければ、新たなものは生まれない。古い修身の教えも理解したうえで、時代に合った新しい道徳も納得しなければとお書初めを見て感じました。
令和7年1月『お供え』
いよいよ令和7年が始まりました。今年が皆様にとって良い年でありますようお祈り申し上げます。さて。今年は巳年。蛇には一般的に嫌われがちでネガティブなイメージもありますが、古来より豊穣や金運を司る神様として祀られることもあり、神聖な生き物として認識されてきたそうです。巳年、皆様方の生活が豊かでありますようにと願っております。新年が始まり皆さんは初詣に行かれましたか。喪中のわが家ですが葬儀後50日を過ぎればよいというお話を聞き、神田明神に参拝しました。二十数年前父(定七)の発案で一族でお伊勢参りをしました。その時に父からは手水舎での作法や神宮での願い事は個人のお願いはダメで、一年のお礼もしくは何かの誓いをするのだと教えられました。以来、25回続けている年末の伊勢参拝の際は、必ず一年のお礼をさせていただいております。今年は都合により東京大神宮にての参拝でしたが、申し込みの際のお願い事は「神恩感謝」でした。神社やお寺に初詣に行かれた際には、お賽銭をお供えしたと思います。このお賽銭の意味は感謝の気持ちとしてのお供えが由来。その起源には諸説があるようですが、現在のように神社にお参りするとき、お賽銭箱に金銭でお供えることが一般的となったのはそう古いことではない。もともと、御神前には海や山の幸そしてお米は特別なお供え物と考えられていたそうです。つまり、現在のお賽銭をお供えするということは神仏に感謝する形を金銭でお供えするということです。モラロジーでも同様な行為を報恩と称しています。この報恩の意味は神仏への感謝と同様に、国や家そして道徳を教えていただいてきた先輩方に感謝することを金銭等でお供えすることです。モラロジーを学び。人様のお役に立ちたいという気持ちが湧いたときにその費用として自分の力のできるだけのことをすることと先輩から指導を受けてきました。日々の生活の中で目に見えない様々なことへの感謝の気持ちを報恩・お賽銭という形で現しましょう。
令和6年12月『インバウンド』
10月25日小学校の校外学習で浅草・東京タワーに行ってきました。浅草では観光ボランティアの方に説明を受け、改めて浅草寺を知りました。東京タワーでも予想通りインバウンド(観光業界で使われる訪日外国人という単語)がものすごく多く、改めて驚きました。Web上ではこの外国人客の日本に対しての感想が多く書かれています。日本人は礼儀正しく、日本人同士の尊敬の念を外国人に対しても尊敬の念を感じた。マナーが良くサービス精神が高い。公共交通機関が時間通りに運行するなど外国人は驚くようです。しかし、今の本当に姿は違ってきているように思えます。今年の部活動の指導で練習や試合で部員が集まらないことが続いています。これは勤務校に限らず、中学校の先生も他校の高校の先生方も口をそろえておっしゃっています。中学校では部活を休んでも強く指導できない。休むのは当たり前。親からのクレームがある等。勿論、こんな学校ばかりではないと思いますが、意欲的に活動してきたはずの部活動でさえこんな状態です。以前に自己中(自己中心主義)という言葉がはやりましたが、今は行き過ぎた個人主義の上に強い自分本位の考え方が重なっている状態だと思います。自分が大事で自分が良ければよく、周りや他の人間のことなど考えない。おそらく、小・中・高校生は親や周りの環境の影響でこんな子供たちが増えていると思います。島国の日本は均一社会で日本人はみな同じルール・モラル・マナーを持ち合わせていました。しかし、現在は多様性社会といわれそれぞれ違う考え・行動が許されています。男女共同参画に関する条例がない千葉県では、今年「多様性尊重条例」なるものが制定されました。多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の実現を図るためという趣旨は理解できますが、今以上に様々な考えの人間が出てきて日本の誇るべき文化・社会が壊れていきそうな気がしてなりません。まだまだ外国人が驚くような日本ですが、果たして「おもてなし」の精神は今後も続くことができるのでしょうか。教育に携わっている私は、もうひと頑張りかなと思います。
令和6年11月『昔話』
10月20日(日)に上総モラロジー事務所の生涯学習セミナーに出講してまいりました。最近では珍しく一般対象の4コマでのセミナーでした。また、テキストが10月から新しくなり、初めての講義でした。講師になってから3冊目の変更。一般の方々に分かりやすくという趣旨で変わったそうです。前のテキスト(心新たに生きる)の最後(日々新たに―最高道徳実行のすすめ―)に「道徳的因果律の確信を持った生き方」と掲載されていました。この道徳的因果律について大塚信三先生は「今日まで、道徳教育が軽視さてきたのは、道徳実行の効果について人々に確信を与える科学的研究が不十分であったからであると考えられます。モラロジーは、人間の精神作用および行為とその結果との間に因果律が存在するという立場から、道徳実行の効果を科学的に証明しようとするものです。」つまり、善因善果・悪因悪果・自因自果。善い原因を作れば善い結果が生まれる。悪い原因を作れば悪い結果が生まれる。自分が作った原因が自分に返ってくる。このことを科学的に証明したのがモラロジーの原点です。だからこそ聴講者にこのお話しをしなければと最後の10分にお話ししました。この善因善果の説明が難しいのかテキストから無くなりました。私は昔話でこのテーマを説明しました。昔話「おむすびころりん」正直お爺さんと欲張りお爺さんが住んでいました。正直おじいさんは山でお昼のおにぎりを食べようとしたところコロコロと穴に落ちてしまいました。中からネズミたちの歌声が聞こえてきました。おじいさんは楽しそうなので穴の中へ。そして、ネズミたちがお礼に大きな葛籠か小さな葛籠のどちらが良いですか。おじいさんは小さな葛籠を持って帰り開けてみると宝物がいっぱい。欲張り爺さんが同じように穴にお結びを落とし、お土産に大きな葛籠を選んだところ穴から出るのが大変でしたというお話。昔話から善い行いをすれば善い結果が現れることを聞いてきました。自分に置き換えると13年前の東日本大震災で支援に行きました。帰りに小さな葛籠(感謝)をいただきました。葛籠を開けてみると中に自分の深い思いやりの心が入っていました。
令和6年10月『寛容』
9月14日に事務所主催の靖国神社正式参拝・敬老会を実施しました。正式参拝では本殿にて玉串礼拝させていただきました。本殿は質素なもので、大きな八咫鏡の前にて玉串を礼拝させていただきました。暑い中、我々以外にも参拝者がいらっしゃいましたが、我々は正式参拝ということでドレスコード(ネクタイ着用・女性はそれに準ずる)を決めていました。他の参拝者は全く英霊への感謝の祈りというような服装ではありませんでした。一応、神社の案内には「肌の露出が多い服装や素足での参拝はご遠慮ください。」とあるのですが、猛暑のためかノースリーブのワンピースの女性も玉串礼拝をさせていただいていました。妻が気が付いたのですが、その女性は裸足だったようでした。我々が教えられてきたのは、裸足で畳に上がるのはマナー違反ということ。時代の変化でマナーも変わっていくのは仕方がないと思っていても、疑問を感じました。また、9月9日の朝の番組で中学・高校で「ハーフパンツ制服」増加というニュースがありました。新採の時に当時の教頭との帰り道「大久保さん大変だけれどネクタイを絞めてみるといいよ」と言われました。一つやってみるかと、その後の通勤時にはずっとネクタイを締めてきました。3校目の学校は標準服(行事の際には制服で、通常は自由)だったので、制服検討委員会を立ち上げ何とか制服化をめざしました。やはり学校の場では乱れた服装での教育は不十分になると思います。教える側も教えられる側も襟を正して授業に臨まなければならないという考えでした。高校生のころからT(時間)P場所)O(場合)を言われていました。服装のTPOとは日常生活において置かれた状況にふさわしい常識的な服装・礼儀作法を守ることで、現在の自由・多様化の下では守られないのでしょうか。ただ、救われた思いは、その番組で中高生の本音で「ハーフパンツの制服はあり・なし」のアンケートを取ったところ、あり24人、なし26人でした。自分の中にこの時代に合った「寛容」さも必要なのかなと思った出来事でした。時代が変化しても日本人のモラル・マナーは残ってほしいものです。
令和6年9月『AI』
7月の感謝の集いの松浦講師のお話よりAIを使ってみました。まず、モラロジーを調べてみました。『モラロジー(Moralogy)は、日本における道徳や倫理の研究・教育を指す言葉で、特に「モラロジー研究所」が提唱した概念に関連しています。この研究所は、山本七平によって1961年に設立され、道徳や人間性に関する学問として発展してきました。モラロジーの基本的な考え方は、以下のような要素を含みます。人間関係の重要性: 社会の中での人間関係や他者への配慮を重視し、人間の成長や発展に寄与する考え方。道徳的判断: 人がどのように正しい行動を選択し、倫理的に生きるべきかを探求すること。 教育的アプローチ: モラロジーは、学校や家庭での道徳教育を通じて、次世代の育成に寄与することを目指します。実践的な道徳: 理論だけでなく、実際に人々がどのように道徳的行動を実践するかに焦点を当てる。モラロジーは、社会の倫理観や道徳観を深めることを目的とし、個人だけでなく、コミュニティや社会全体の健全な発展を促進する役割を果たすとされています。』間違いを発見-1926年廣池千九郎により創立-。また品性を調べると『「品性」とは、人の性格や人格、特に道徳的な側面を指す言葉です。この概念は、個人の行動や態度、倫理観、価値観などに関連しており、他者との関係においてどう振る舞うかに影響を与えます。品性は、以下のような要素を含みます。道徳的な価値観: 正しいことと間違ったことの判断、他人に対する配慮や尊重などが含まれます。誠実さ: 真実を語り、信頼できる行動をとること。嘘や不正を避ける姿勢も重要です。責任感: 自分の行動に対して責任を持つこと。他人や社会に対しても責任を持つ態度が求められます。他者への配慮: 他人の気持ちや状況に対する理解や共感、助ける意欲などが含まれます。自己制御: 感情や衝動をコントロールし、冷静に行動することができる力。勇気: 正しいことを行うために困難に立ち向かう強さや決断力。品性は、人々の評判や信頼に大きく影響し、人間関係や社会的な相互作用を円滑にするための基盤となります。また、品性は教育や経験を通じて形成されるため、個人の成長や発展において重要な要素とも言えます。』やはり使う側の教養が試されることがわかりました。
令和6年8月『堅義加行』
6月19日にお世話になっている奈良薬師寺小林澤應録事のところをお尋ねしました。奈良には平成29年(7年前)まで毎年のように伺っていました。妻がブラタモリのファンで神社仏閣・お城が大好きということもあって5年近く毎年伺いました。今回は澤應さんから堅義加行(りゅうぎけぎょう)のお話をお聞きしました。薬師寺の僧侶の本業は学問。11月14日に法相宗の最重要の法会の慈恩会の夜に口頭試問(堅義)で日頃の成果が試されるそうです。合格すると已講(いこう)という位に登り、薬師寺の住職・管主になる資格が与えられるそうです。そのかわり失敗すると不浄門から寺を追放されるそうです。現在法相宗ではこの堅義をきちんと行っているのが薬師寺のみとお聞きしました。その行の第一歩が春日大社にお参りし御神火をいただくそうです。薬師寺の僧侶でも神様のところへ行き御神火をいただき、その火の元で二十一夜漬けで受験勉強をされるわけです。加行部屋といわれるところで食事は六時半と十一時半の2回。朝五時半から境内の諸堂を参拝。五日に一度、西ノ京一帯の十三社に参拝。そして、勉強のため夜中の12時をまわっても半ば眠り半ば醒めて暗誦を続ける。1日に睡眠時間は2時間ほど。その睡眠も横になることは許されず、背もたれに寄りかかり座睡。そして、堅義が無事終了すると、春日大社へご報告に行くそうです。仏教徒も神様に対して祈るということ。モラロジーの考えの元には自然の法則と表現し、我々はその自然の中で生かされて生きているという考えです。言葉に変えれば{神}ということになると思います。伊勢神宮、天皇陛下、奈良薬師寺が我々の安心、平和、健康をこの神様に祈っていただいています。廣池博士の書かれた論文の最初に「天地剖判して宇宙現出し、森羅万象この間に存在して、いわゆる宇宙の現象を成すに至れるは、偶然にして然ることは出来ないのである。必ずやその原理もしくは法則ありてここに至れるものである。故に宇宙間に産出してこの間に生存するところのわれわれ人間としては、この宇宙自然の法則に従わねばならぬことは明らかであります。
令和6年7月『霊肉不二万古不易』
6月1日公益財団法人モラロジー道徳教育財団の伝統祭が行われました。私たちが生きていくことを根底から支え、慈しみ育ててくださっているさまざまな恩人、親祖先を思い感謝する日。この財団にある霊堂にはモラロジー発展に協力をしたということで、私の祖父祖母・父母・姉に叔父の分骨が祭られています。その入り口正面には「霊肉不二万古不易」とあります。霊肉不二とは身と心、体と霊魂は分かれていない。そして、万古不易とは永久に変わらないということ。つまり、亡くなられた方々の精神・心は永久に変わらないで我々が受け継ぐということ。そんな1日に靖国神社で事件があったようです。入り口の石柱に赤い文字で「Toilet」と落書きされているのを通行人が発見。中国語を話す男性が石柱に向かって放尿する仕草をした後、スプレーのようなもので文字を書く姿を映した動画がネット上に出回ったようです。根っこにつながるという意識をもたないのか、この国の方々に亡くなられた先人の精神を大事にするということは残念ながら絶対に理解できないと思います。この犯人も自分の生まれた土地・国を大事にするという考えがないから、他国の精神を大事に考えることはできないのだと感じます。ところで以前、小学3年生の男児が大東亜戦争に興味を持ったようで、ユーチューブで「大東亜共栄圏占領下の人々の本音」を見ていました。ユーチューブの中では我が国が東南アジアを欧米の植民地から解放したという見方と自虐史観的な見方の両者があるようです。歴史の見方には様々な方向から見ることができ、多くの意見を知ることが重要だと思います。そういう意味で小学生が先の戦争に興味を持ち、学んでいる姿を何となくホッとしました。私は戦地に行った父や東京大空襲を経験した父母から戦争の話をほとんど聞くことができませんでした。それは、敗戦ということと戦争に対する責任を負うという意味で口を開かなかったのだと思います。自国を愛し優しく思いやりのある気質は、今も昔も日本人の根っこにあると思います。霊肉不二万古不易の精神を大事にしていきたいものです。
令和6年6月『Z世代』
26日の高校部活指導で3年生最後の試合後の挨拶を行いました。3年生、特にレギュラーの選手には随分怒鳴ったことを謝りました。今の小学生から高校生まで怒鳴られた経験が少ないと感じています。パワハラということで親も先生も強い口調で注意できない現状があります。何となくこれでは子供たちが弱くなると思い、昭和の監督を自負している私は意識的に大声をあげていました。5月3日にBSフジプライムニュースが『日本の新たな病巣か… 退職代行で入社日退社 世代間の溝の埋め方は』というテーマでした。先月号の内容だったので興味深く見ました。その中でZ世代について意見がありました。Z世代とは20代前半から10歳前後の年齢の人が該当するそうです。特徴は少子化により上の世代のような厳しい競争を経験せず、低成長の世代でもあるので現実主義的な面があるそうです。番組で原田曜平氏は「とにかく若者の人口が減っていますから、企業にとってZ世代の希少価値が高くなっています。コロナ禍でも新卒採用を増やした企業も多いです。そのため、Z世代の就職に対する危機意識は薄い。楽観的に考えている大学生が多く、入社後も気に入らないことがあればすぐに辞めてしまう傾向も強い。また、『チル&ミー』が日本のZ世代を読み解くカギ。その特徴を表現すると「『チル』とは、『まったりする』という表現。不安や競争の少ない環境で育ってきた彼らは、マイペースに居心地良く過ごすこと、つまり『チル』を大切にする傾向が強いですね。」大学の一般入試で受験する学生が49%。失敗しない、無理しないを優先するZ世代。さらに原田氏は「Z世代の保護者はとにかく優しくて怒らない。子どもの意志を尊重し、自由にさせる育て方をしている家庭が多いです。」親も子供の意思優先で我慢とか失敗させるという厳しさを教えない。気がつくとんこんな時代になっていました。さて、古希を過ぎ高校生を怒鳴っている私には理解し難いし、若者はこれで良いのか不安になります
令和6年5月『4月1日』
いよいよ令和6年度が始まりました。その1日、3月中に研修を終えた新人が会社を退職したそうです。配属先が結構厳しい環境で初日から心が折れた新人。そして、退職時には退職代行サービスを使って会社に伝えるそうです。ある代行サ-ビスでは4月1日だけで4人の新卒の退職代行を行い、4月~5月で100件を想定しているそうです。自分の口で会社や相手に伝えることができない。時代が変わりましたね。商業高校に勤務し進路指導に関わったとき、人事の方との関係もあり生徒には3年我慢するようにと伝えていました。学校から推薦して入社したということは「最低限の責任がある」としてそう伝えました。社会人とは「社会的なルールやマナーを理解・遵守し、役割や責任を果たす人」。そして、社会性とは「集団生活や人間関係の構築において欠かせない能力」です。現在の若者の社会性はどうなっているのでしょうか。このような青年たちを受け入れなければならない時代なのか疑問に感じます。また、中学の卒業式の卒業生男子がお化粧をするそうです。息子たちからはもうそういう時代だと言われました。インターネットで調べると「中学生男子・卒業式・化粧」というテーマが載っています。現職の頃は高校生に頭髪指導と言って髪を染めることさえ違反としていました。定期考査中に先生方に生徒の髪を見てもらい、茶色い生徒には指導をしていました。自分でも少し違和感がありましたが、ルールに従わせることを優先にしました。過去にこんな時代があった今、中学生男子がお化粧をするということはなかなか受け入れられません。モラロジーの考え方で孝行とは親・祖先に安心をして貰う事といわれています。この青年・中学生の親・祖先はこのような様子を見て満足するのでしょうか。そんなところに答えがある気がします。モラロジーで最近よく耳のする言葉に「祖述」があります。祖述とは遺志を受け継ぎ、それを時代に合わせて発展させること。まず、親祖先の遺志がどこにあるのか。是非その遺志を受け継いでもらいそれを発展させ、人生をさらに豊かにしてもらいたいものです。